貧困ビジネス

著者:門倉貴史
底なしの不況。貧困層は急増している。無差別殺人や凶悪犯罪のニュースで、犯人の職業が「無職」と出ると、やっぱり貧困は人心を荒廃させるのだと胸が痛む。
この本では、さまざまな貧困ビジネスについて取り上げ、その恐ろしさについて説明している。敷金、礼金の要らない「ゼロゼロ物件」がなぜ儲かるかがわかった。
ほかにも、多重債務者にニセの養子縁組をさせてさらに借金をさせる「リセット屋」。世界に蔓延する人身売買、賃金のピンハネ、安物の危険などなど。
特に筆者が一章を割いて述べるのが「台頭する貧困対応型セックス・ビジネス」。私は女なので風俗にお金を使わないし、風俗で稼ごうにも稼げないお年頃なのでかなりどうでもいい世界なのだけれど、風俗の業界でも売り上げ、給料低下がはなはだしいという。
一部の男性や、業界にかかわる人にとっては切実な問題らしい。こういうところからもまた人心の荒廃が生まれてきそうだ。
一番こわかったのは、中国製の安物の醤油の中にかなりの割合で頭髪のアミノ酸が使われているということ。
気持ち悪すぎる。中学の家庭科の教科書に「髪の毛」食べると気が狂う、って書いてあったような気がするんだけど・・・
中国製の醤油を買うことはなくても、中国から輸入された加工食品に使われている可能性はあるってことよね?!
最近、「激安弁当」がテレビで話題になっている。198円とかのもある。私はボランティアで60人分の弁当作りをしたことがあったけれど、容器も合わせて一人300円~350円で作るのもけっこうしんどかった。(人件費はボランティアなのでゼロ)
安い弁当の裏側で、安い賃金で人が働かされ、農家が泣いているかもしれない。安全も不安。安いほうがうれしいけれど、どこかで歯止めをかけないと、しわよせが怖い。
カテゴリー: ノンフィクション
日本の10大新宗教 島田裕巳
日本の10大新宗教

筆者は宗教学者の島田裕巳氏。
天理教、大本、生長の家、天照大神宮教、立正佼成会、霊友会、創価学会、真光系教団、PL教団、真如苑
・・・など、いわゆる「新興宗教」(筆者はあえて「新宗教」と呼んでいる)と呼ばれる宗教の成り立ちや組織分裂、事件と弾圧などについて、客観的な視点から教えてくれる書。
自分が特に信仰を持たない人間なので「新興宗教」というものに対してなんだか怪しげなものを感じていた。
駅前で「あなたの幸せを3分間祈らせてください」と言われて「いいッス」と逃げたことも数回。
今も昼間家にいると、勧誘っぽい訪問があったりして「要らないですー」とわざとトンチンカンに答える。
要するに、偏見を持っているのです。
しかし、この本を読むと、明治以降に生まれた新宗教ももとは前からあった宗教からの分派であることがわかる。それによく考えればすべての宗教は新宗教から始まり、弾圧などの憂き目に遭ってきたのだ。
少なくともこの本に挙げられている宗教に対しての偏見はかなりなくなった。有力な学園を作っているところもあるし。(高校野球が強いところが多いですね)
これは前から思っていたのだけれど、改めて奈良県は天理市に行ってみたくなった。独特の雰囲気の宗教都市らしい。
特に信仰は持たないと言ったけれど、宗教的なものは好きです。神社仏閣、仏像、教会、宗教的な読み物も。
瀬戸内寂聴先生は「良い宗教とね、悪い宗教の見分け方はね、お金を取るか取らないかってこと。お金を取る宗教はよくないです」と言っていた。
たしかに怪しげな宗教に入ると身ぐるみはがされそうな気がする。
あと、個人的には政教分離をしっかりとしてほしいと思う。
「幸福実現党」は次の総選挙でどこまで躍進するんでしょうか?
獄窓記 山本譲司
獄窓記
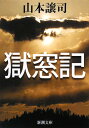
筆者は元衆議院議員の山本譲司氏。2000年に政策秘書給与の流用事件を起こし、01年に実刑判決を受けた。
433日に及ぶ獄中での生活を綴った著。新潮ドキュメント賞受賞作品。
とても読み応えがあった。2000年の事件のことはあんまり覚えていなかったけれど、この本を通じていろいろと考えさせられた。
まずはとても刑が重かったということ。執行猶予つきが予想されていたけれども、実刑になってしまった。同じ様なことをしている人(辻元清美氏・田中真紀子氏)は刑務所に入るまでにはならなかったのに(辻元氏は執行猶予)。
一罰百戒とはいうけれど、ちょっと気の毒に思わざるを得ない。もちろん、詐欺をしてはいけないが。
服役するちょっと前に第一子が生まれたというのも悲劇。
服役した著者の刑務所での仕事は、障害を持った同囚たちの介助訳だった。
汚物にまみれる、果てしのない作業。受刑者に人権なんてあったものではなく、(あたりまえなのかもしれないけれど)劣悪な環境に耐えなければならない。
私は単純。「文は人なり」と思って、文章から読み取れることをすぐ信じるのだけれど、山本氏は悪いことはしたけれど、腐ってはいない人なんだろうと思った。
奥さんとの信頼関係がずっと崩れなかったのも一つ。
率直に反省し、潔く刑を受けたことが一つ。
誰が見ても「厳しすぎ・長すぎ!」の服役の期間を、自分が生まれ変わった契機として前向きにとらえていることが一つ。「障害と犯罪」の問題を新たなライフワークにしようとしている。
もちろん、前向きになるには待つ家族の力が重要だとは思うけれども。
誰だって罪を犯す可能性はある。罰を受ける可能性もある。でも、そこで自分が反省して生まれ変わればまた新しい目標を持って生きていけるもんだ。人間の底力に感心した。
いまだに「自分は悪いことをしてない!」と反省の色ナシの辻元氏と山本氏が早稲田で同じゼミだったとか。
まあ、高潔だからといって幸福とは限らないけれど、辻元氏が活躍するのはなーんとなく面白くないなあ、と思ってしまった。
フィンランド 豊かさのメソッド 堀内都喜子
フィンランド豊かさのメソッド

筆者はフィンランド系企業に勤務しつつ、フリーライターとして活動する堀内都喜子氏。
フィンランドは教師の育て方がすごい
でフィンランドという国についてまた興味が出てきたので読んでみた。
学者の視点というよりも、フィンランドの社会で生活した視点で書かれていて、フィンランド人の気質や社会のシステムが、日本とはずいぶん離れていることがわかる。
(似ているところもあるにはあるが)
国際的な学力調査(PISA)でもトップ、国際競争力ランキングでも何度も一位になっているフィンランドの秘密はどこにあるのか。
印象としては「徹底的に現実主義で、実利主義」という感じ。IT化は日本よりずっと進んでいるようだし、教育に関しても、自分の将来を見据えて、社会で有用な人物となるため子供たちは育てられているかんじ。
人間関係も、グレーな部分がなく、対等を重んじるとか。「トイレありますか?」だけではトイレは貸してもらえない。「トイレを貸してください」といわなきゃ。
日本人と似ているところは、あまり喋らないこと、家の中で靴を脱ぐことぐらいか?
税金がものすごーく高いけれど、その分大学まで学費はタダ、社会保障もしっかりしていて、女性が働くのは当たり前。(大統領も首相も女性!)
全部をマネするのは無理だし、フィンランドにも問題はあるけれど、いいところを日本の社会に取り入れてもいいんではないだろうか。
税金が高くても、使途がガラス張りで無駄がなくて、将来安全安心、なら国民はそう不満を持たないと思うけれどもね。
フィンランドといえばかもめ食堂という映画がある。

やや少女趣味だけれど、私はけっこう好きです。おにぎり食べたくなります。
遺品整理屋は見た! 吉田太一
遺品整理屋は見た!

以前、
おひとりさまでもだいじょうぶ。
を紹介したときに、著者の吉田太一氏が社長を務める「キーパーズ」の方からコメントをいただいた。
この本も、面白そうだったので読んでみた。
まず思ったことは、「人のいやがる仕事をする人はえらいな。」という単純な感想。素直に尊敬する。ウジの山、一面のゴキブリの壁、煙状のハエ、血の海、ゴミ屋敷。
おくりびと
という映画(話題になったけど、私としてはイマイチだった。)の中で、納棺師の夫に妻の広末涼子が「さわらないで!汚らわしい!」と言ってたのを見てかなりの違和感を覚えた。
いろいろ偏見はあるんだろうけど、誰かがやらなきゃいけない仕事はあるんだから。
躊躇しながらも果敢に自分の仕事を遂行する著者とスタッフたち。しかし、身内でも部屋に入れない、さわれない、という状態で死にたくはないと思った。もちろん自分の身内もひどい状態であってほしくない。
本の内容はしかし「ひどさ」が中心ではなくて、人の死んだ後から見える人間の悲しさ、孤独、人間関係。
遺したものからその人の生き様が見える。でも「孤独死」した人の遺したもので、心温まるエピソードはほとんどない。
自殺の後始末も大変。死んだ後も人に多大な迷惑をかけるのはよくない。自殺するときはそういうことも考えなければ。(いや、自殺しないほうがいい)
あとがきに「いつ自分が死んでも、残った家族や周囲の人に迷惑をかけないように用意しておくということは『充実した今を生きる』ためにたとても大切」
だと筆者は述べている。兼好法師、鴨長明も言ってたように死は何時くるかわからない。
絶対人に見られたくないコレクションなどは、ほどほどにしておいた方がいいですよ。
フィンランドは教師の育て方がすごい 福田誠治
フィンランドは教師の育て方がすごい

著者は福田誠治氏。前に競争やめたら学力世界一
を読んで、フィンランドの教育の柔軟さと豊かさに興味を持った。
教育は百年の計。国を作る重要な土台だと思うのだけれど、どうも、日本は教員の質が問題視されているイメージ。教員免許更新制度なるものまで出来たけれども、教員の質の向上に功を奏するかは疑問だ。
私も教員免許を持っている。あと数年したら、講習を受けなければ教壇に立てない。受講料は自費。県庁所在地の大学まで通う必要がある。いったいどんな有用な講習をしてくれることやら。
日本では、大学で教員免許を取ることはそれほど難しくない。教育実習(私は2週間だった)がしんどいだけで、あとはちょっと余計に単位を取ればそれでいい。
本の題名にもあるように、フィンランドでは教師になるのは大変である。「とりあえず免許でも持っておこう」なあんて気持ちでは絶対に資格は取得できない。
フィンランドでは…
・ 教育実習は20週。
・ 教師は修士の資格を持つ。
・ 教師は情報伝達者や講義者でなく、助言者であり学習案内者である。
・ 教師や学校の善し悪しの外部評価はない。
・ 学校査察も教科書検定もない。 などなど。
自由ではあるけれど、自分で教材を開発して、教え込みをせず生徒を主体に授業を組み立てるのは、とても大変なことだ。
日本でははっきり言って、「教師用指導書」があれば、ちょびっとの準備で授業を成立させることは可能だ。教科書を読むだけー、板書するだけーの教師にこれまで当たったこともある。
フィンランドの教師は「授業」が主な仕事で、帰宅時間もものすごく早い。
日本では?「教師の仕事の半分以上は雑用だ」という現場の教師のボヤキを聞いた事がある。
教材研究に十分な時間をとれないことは多いだろう。
読み書きなどの基本を徹底するのがいいのか、フィンランドのように創造性を重んじればいいのか、学力調査をしたりして結果責任を問えばいいのか、フィンランドのように説明責任を負えばいいのか、どちらがより良いかは、わからない。
フィンランドの教育にも、問題点はあると思う。
でも、今の日本の教員のあり方を考える上で、他の国の実践を参考にすることは重要だと思う。
個人的な意見を言えば、教員の質を上げるには、免許更新制度よりも、一切のコネ採用を無くした方がいいと思いまーす。
北京陳情村 田中奈美
題名:北京陳情村

著者:田中奈美
第15回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞作。
五輪で沸き立つ中国北京。土地の強制収用、冤罪、役人の腐敗などを中央政府に訴えるために、中国全土から「陳情者」が集まった村がある。解決率わずか0・2%の「陳情制度」に命を賭けた彼らの姿を、女性ルポライターが潜入し、接近し、取材する。
毎日、政治に対する不満がテレビとかラジオとかで語られているけれど、「いやー、日本はいい国だ。」と思わされてしまった。
中国はコネ・賄賂社会で、警察も、役人も、まるで頼りにならない。
「言論の自由」もない。
言ったもん勝ち。(勝つ率は低いが)ごね得。謙虚さを美とする日本人なら中国では3日で身ぐるみをはがされそう。
また中国の印象が悪くなってしまった。やっぱり、文化、宗教、道徳をないがしろにすることは国を不幸にすると思う。
筆者のエネルギーにも脱帽。あとがきで筆者は「この国には、どうにもならないような混沌と不条理が少なくない」としながらも、アグレッシブに生きる中国の人々から我々は学ぶところがあると言っている。
確かに、日本人は「おかしいよ」と思っても訴えないことが多い。エネルギー不足かも。
しかし、漢文で勉強したあのすばらしい中国の倫理は何処へいったのか?
寂しい限りだ。
エビと日本人〈2〉 村井吉敬
題名:エビと日本人(2)

筆者:村井吉敬
家族にエビアレルギーがいるので、エビは好きだけどあまり食卓に出さない。
この冬に、地物のエビを漁港の近くで焼いて食べたのはとても美味だった。
しかし、スーパーで日本産のエビを見かけることはまずない。「ベトナム」「インド」「インドネシア」「ミャンマー」などなどだ。
この本を読むと、ちょっと食べる気が失せる。
筆者は世界中、日本中のエビの現場を追い、エビをめぐる現状や問題点を指摘している。
結論としては、日本人はエビを食べすぎだって!ということ。しかし、世界中でエビをもっとも消費するのは日本人ではないけれど。
エビを食べ過ぎない方がいい理由は・・・
1 養殖エビはマングローブ林を破壊して成り立っているから、環境上資源上よろしくない。
2 エビに使われている抗生物質は多く、安全な食べ物かどうか怪しい。
3 極端といえるほどの輸入依存である。
食糧自給率が50%を割り込む日本は、もっと身近な食糧生産を心がけるべきだという意見だ。
今日のスーパーのチラシに「エビフライ(ベトナム産)」という冷凍食品が載っていた。あとは揚げるだけ。
その裏では、恐ろしく安い賃金でベトナムの人がエビの殻をむき、背わたをとり、衣をつけてくれている。
豊かな食生活を享受していることを、ちょっと反省させられる一冊だった。
経済系、食物栄養系の大学の小論文対策にいいかも。
徹底抗戦 堀江貴文
徹底抗戦

筆者:堀江貴文
ホリエモンについても、ライブドア事件についても、まるで興味はなかった。ホリエモンが目立っていた2004年~2005年ぐらいのときは、忙しくてテレビも見ていなかったから、彼について思うことは何もなかった。
前にも紹介した
平気で他人の心を踏みにじる人々
などで、ちょっと彼に興味を持ち、「人格がよろしくないと一部で言われているホリエモンはどのような文章を書くのか?」と思って読んだ。この本の宣伝でテレビにも出ていた。拘置所でスリムになったのに、見事にリバウンドしている。
印象は・・・この人はずいぶん率直で「身も蓋もない」言い方をする人だということ。人間の心の機微というのが少ないかも。拘置所生活の中で、寄せ書きを社員からもらって泣いたというエピソードがあったけれど、泣いたのが物心ついてから初めて!だと。
両親の話題でも出てくるかと期待したけど、全くなし。没交渉なのかな。
反省は、していない。自分が悪いことをしたとは思っておらず、悪いのは宮内氏と、亡くなった野口氏という書き方をしている。
日本の検察は一罰百戒主義?で、ひっかかったホリエモンは気の毒な面もあると思う。
確かに、彼には悪いことをしている認識はなかったのかもしれない。
証券取引とか、全く意味がわからないので、ホリエモンのしたことを判断することはできないけれど、まあ、彼の言い分も聞いてあげていいと思う。
しかし、拘置所で性欲を処理するエピソードには閉口。書かなきゃいいのに・・・
ルポ 高齢者医療 佐藤幹夫
題名:ルポ高齢者医療

著者:佐藤幹夫
医療制度はどんどん変わっていっている。私が子どものころ、老人医療費はタダだったはずだけど、2006年の後期高齢者医療制度の創設により、2008年4月以降、75歳の高齢者全員から医療費を天引きで徴収することになった。
高齢者イジメと、マスコミでもさかんに報道された。
診療報酬も史上最大のマイナス改定になって、病院も大変みたい。
長寿になったのは医療技術が発達したからで、喜ばしいこと。でも点滴とか栄養注入とか、技術がポピュラーになったころから、治療を名目とした縛り付けも行われるようになったとか。
筆者によれば、限界集落になって医療も手薄になると、自己の住む地域に対する誇りの喪失がもたらされ、不公平感と不寛容が蔓延するという。
私の実家のあたりも高齢化していて、村に小学生はゼロ、老人ばかりだ。「限界集落」に近いかもしれない。
またまた暗澹たる気持ちになる。
しかし、この本では、その中でも「がんばっている」病院についてルポしている。
地域全体をとりこんで患者と家族を支えようとしたり、病院が顔の見える地域包括医療を目指して地域をマネジメントしたり。
病院での治療か在宅治療かという二者択一ではなく、在宅支援や地域支援を地域で行うことが重要だとしている。
でも結局は、人が頭と体を一生懸命動かすしかないってことか。
現状のままで・・・&負担は国民の皆様に・・・というお役所の発想には期待できない。
こういうところで、マスコミ、政治家は国を動かしてほしい。