竜馬がゆく(1)新装版
~
竜馬がゆく(8)新装版

作者:司馬遼太郎
今年はNHK大河ドラマの影響で竜馬ブームですね。「天地人」は見なかった私も(見ている夫の横で本を読んでました)「龍馬伝」は見ている。
福山雅治って20年間ずーっとカッコいいよなあ…と関心しつつ。
(「JIN」というドラマで竜馬を演じていた内野聖陽も巧い役者だった)
さて、『竜馬がゆく』は過去に読んだ本。今回のドラマの影響で読み返してみようと思い、本棚を探してみたらあった。もしかして捨てたかな?と思ってたけど…
歴史オンチの私が、唯一最後まで読み通すことができた歴史小説です。
司馬作品らしく、説明的なところが多いので、その辺は眠ーくなってしまうんだけれど、竜馬の人間性をあらわすエピソードは面白く、頭に残っている。
羽織の紐をかみ、それを振り回すのが癖で周囲に唾が飛ぶ…とか。それでも女性にモテるとか。
それまでの日本人がやろうとしなかったこと、思いつきもしなかったことを実現しようとした竜馬。型にはまらぬ発想はどういう環境から生まれてくるのか、それとも生まれ持ったものなのか…
魅力的な人物ゆえに、とても面白い小説になっています。
さて、都合により、今日でブログをしばらくお休みします。再開の時期は未定。今まで読んでくださってありがとうございます。
また逢う日まで。
月別: 2010年1月
波打ち際の蛍 島本理生
波打ち際の蛍

作者:島本理生
主人公の真由は現在休職中。元恋人のDVが原因で心を病み、今はカウンセリングルームに通っている。
同じくカウンセリングに通う蛍という男性と知り合い、徐々に二人は距離を縮めていく。
しかし真由は元恋人のDVが頭をよぎり、蛍に本当に心を開くことはできず、そんな自分に苦しむ。蛍は我慢強く真由を思い続ける・・・
といった内容。恋愛のことが90パーセントを占めている。まあそれはよい。未婚の若い女子の頭の中は半分以上恋愛で占められているのが実際だから。
ストーリーはありきたりだけど、ディテイルは島本氏らしくとても繊細。過去の出来事を引きずって相手のことを過剰に窺ったり、身体の感覚の描写はうまいなあと思う。
しかし、「蛍」の人物像が明確につかめなかった。カウンセリングに通うほど重症でもないし、(たぶん)元カノとも「友達」として平気で逢う。でもって、真由に身体のふれあいを何度も拒否されても非常に優しく、辛抱強い。
少女漫画に出てくる男の子みたいな感じ。(昔のしか知りませんが)
いい人だけど、好きになれないタイプだった。元カノと逢うという時点で不合格。友達に戻れるくらいなら真剣な恋じゃない!
などなど思いましたが、ディテイルを楽しめば、よい小説だったと思います。
心理療法個人授業 河合隼雄 南伸坊
心理療法個人授業

先生が河合隼雄氏、生徒が南伸坊氏となって、心理療法について13講にわたって授業をしている。
対談形式ではなく、生徒の方も先生の方も文章で要点をまとめているので、内容が濃い。
生徒の南氏は虚心坦懐に授業を聞くから、河合氏の方も難しい話をわかりやすくしてくれる。
心が頑丈な私はカウンセリングにはたぶんお世話になることはないし、臨床心理士になるつもりも全くないけれど、人間関係においてはカウンセリングマインドは大切など思う。
そんな視点から重要だと思ったのは「相手の話を真剣に聞くこと」。私は人の話を聴くのが好きだけれど、喋るのも好きなので、聴いているつもりがつい自分の話をしてしまう。
相手が悩んでいたり苦しんでいたりするときには、心から耳を傾けなければ、と思った。
他にも「死にたい」という人は死にたいということでしか「生きたい」気持ちを表せないとか、「妄想」を持つ人が薬で妄想を取り払っても、その人の人生にとってそれが本当にいいことなのか、など、ハッとさせられる記述があった。
クライアントと治療者の関係(恋愛関係など)も興味深い。
臨床心理士になりたい人はとても多いらしい。大学でも心理学系は非常に偏差値が高いし。
河合氏によれば「命がけの仕事」。たしかにあまり軽い気持ちでなって欲しくないし、できない仕事だと思う。
本当は親や友達、教師がカウンセリングマインドを持っていれば理想的なんだろうな・・・
かけら 新津きよみ
かけら

作者:新津きよみ
ちょっとサスペンス。
主人公は3人の38歳の女性。
涼子は雑誌で主婦の読者モデルとして活躍し、紀子は主婦業にいそしみ、理恵はキャリアウーマンとして邁進。接点はまったくない3人だが、共通点はただひとつ。むかし、同じアイドルの「おっかけ」をしていた。
涼子のもとには過去の彼女の写真が送られてきたり、お店で無断で写真を撮られたりする。
紀子はデパートのイケメン店員にはまり、買い物しまくって消費者金融へ。
理恵の友人の同時通訳者のしおりはある日突然謎の失踪をする。
昔のアイドルだった男は今は探偵。理恵はしおりを探すべく、その探偵事務所を訪れる。
3人とも表面的には幸せな生活を送っていそうだけれど、過去に捨てたい思い出があったり、実家との葛藤があったり。買い物しまくるというのも、何か満たされないものがあってのこと。
女性のちょっとした不満や不安を拡大してサスペンス仕立てにした感じだった。
読み物としてはちょっと物足りない気もするけれど、読んでるときは楽しかったので、2時間ドラマを見るようなつもりで読むといいかもしれません。
私は二時間ドラマ見ないけれども…マッチの「岡部警部第4弾!」というのを新聞欄で見て、マッチが頑張ってると思うとホッとするぐらいです。
蒼い乳房 谷村志穂
蒼い乳房

作者:谷村志穂
谷村志穂が、20代のころから最近に至るまでの間に書きついだ十の短編集を自分で選んで集めたもの。
ほぼ、恋愛小説。
谷村志穂の恋愛小説は私の分類だと「モテ系」。たぶん彼女自身、あんまり男に不自由した経験がないと推測する。
彼女の小説を好きか嫌いかと聞かれると、ファンとはいえない。今回の自選短編集も、ハッとするような作品はなかった。残念ながら。
定時制高校を舞台とした初恋物語、不倫の恋の中の幻滅、失恋をきっかけに大人になる女子大生、黒人の恋人に振り回される女性などなど。
谷村氏の小説のなかでおそらく一番有名な『海猫』の外伝も。
(『海猫』は数年前読んでみたけれど、忙しかったのとなんか好きじゃなかったのとで挫折している。ゴメンナサイ。)
『海猫』は映画にもなったらしい。仲村トオル出演、というのには惹かれるけれど、伊東美咲の演技が…浜村淳も酷評していたので観る気になれず。伊東美咲さんはとっても美しい方ですけれどね。
なんで好きじゃないんだろう、谷村志穂氏の小説。たぶん、「男に甘い」って気がするんだよなー。どことなく。純情な男性は確かに多いけれど、失恋小説にしても男の卑怯さ、ダメさ加減をもっと描いてくれれば共感できるかも。
バナナは皮を食う 壇ふみ選
バナナは皮を食う

昭和23年から昭和32年にかけて「暮らしの手帖」に掲載されたエッセイから、食にまつわるものを集めたもの。
そのころの日本といえばまだ貧しく、今のように食卓も豊かではない時代。そこにある工夫、節度ある暮らし、ささやかな喜びが綴られている。
ごちそうの話よりも「おむすび」「漬け物」の話が興味深かった。
「おむすび」にまつわるエッセイは多かったけれど、手で握ったおむすびがなんといっても旨いと書く人が多かった。確かにコンビニのおにぎりは(特に、後で海苔まくやつ)は冷たーい味がすると思う。
漬け物も、日本人の食卓には欠かせないものだったけれど、今、常に漬け物を出す若い夫婦の家庭って少ないのではないだろうか。私はほとんど出さない。お義母さまが時々持ってきてくださるのを出すぐらい。
昔は実家でも自家製の漬け物が常にあった。あんまり好きじゃなかったけれど・・・
今はたまに「漬け物食べたい!」という時がある。でもスーパーで売っている漬け物にはほとんど「ソルビン酸」と「ステビア」が入っている。この二つは避けているので買わない。
自分で漬ければいいのだけれど・・・これからの課題だ。
この本を読んで「おむすび」「漬け物」が食べたくなった。
エッセイは、面白いものも、つまんないものもあった。「バナナは皮を食う」衝撃の題名だけれど、実際には皮は食べないのでご安心を。
ジェシカが駆け抜けた七年間について 歌野晶午
ジェシカが駆け抜けた七年間について

作者:歌野晶午
舞台はアメリカを拠点にしたマラソンの強化クラブ。
原田歩はアスリートとしての生命を、監督の最悪の指導によって断たれてしまう。
監督を呪い殺したい。できれば自分の分身が欲しいと願う。
ジェシカ・エドルはエチオピアの出身で、歩と同じくマラソン選手。マラソンをやめるという決意をした歩から監督の行状を聞く。
クラブをやめた直後、歩は自殺する。
原田歩の失意の自殺から七年、ジェシカ・エドルが出場したマラソン大会で、監督が何者かによって殺される。監督の手にはジェシカのネックレス。殺したのはいった誰?といったミステリ。
オチ・謎解きは確かに驚きがある。エチオピアの文化・習慣と日本の習慣が違うことを知った。「異文化ミステリ」といったところか。
『世界の終わり、あるいは始まり』『絶望ノート』はとても面白かったけれど、今回はちょっと期待はずれ。
では、小説に愛はあったか? ま、少しありました。
さて、センター試験、今年の小説は中沢けいの
楽隊のうさぎ

から出題されましたね。けっこう中高生に読まれている作品だと思う。私もこの本読んだことあるけれど、その後中学生の知人にあげたし…
まだ問題解いてない。ボケ防止に、今からやってみよう!英語も挑戦してみよっかなー。
戦友の恋 大島真寿美
戦友の恋

作者:大島真寿美
漫画の原作者を主人公にした、連作小説。
主人公の佐紀は漫画家になることを断念した原作者。ずっと一緒に仕事をしてきた編集者の玖美子は、若くして病気で亡くなってしまう。
友達、というよりも戦友だった玖美子。大事な友人の喪失の悲しみは直接には描かれていないものの、じわじわと行間から伝わってくる。
主人公はおそらく30代終わりごろ。連作小説の中では玖美子のエピソードの他にも、若い編集者とのやりとり、同級生の男の子との再会と彼の挫折、いきつけの店の人の病気など、人生の後半にさしかかったものの「憂い」がさりげなく描かれている。
喪失体験。肉親とか、家族とか、友人とか…私だって親しい人を喪うのがどんどん増えてきそうだ。まだ、親しい友人を亡くしたことはないけれど、(26歳の時、大学のクラスメイトが亡くなったが)想像すると怖い。
でも、乗り越えるしかないんだろうと思う。
小説の最後には、明るい光も。そう、何もかも失くしてしまったと思っても、また新しく得るものはあるはず。そう思わないと、生きていけないよね。
雉猫心中 井上荒野
雉猫心中
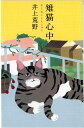
作者:井上荒野
主人公は知子という主婦と、晩鳥という男の二人。
エピローグとプロローグがあり、第一章と第二章に分かれている。
第一章は知子の視点から描き、第二章は晩鳥の視点から描いている。
何を描いているかというと…まあ、姦通・不倫。昨日もそんな小説を紹介したような。
知子は中学教師の夫を持つが、その夫がなんだか変態ぽく、神経質であったかみのない印象。家に迷い込んできた雉猫をきっかけに晩鳥という男(古書店主)と知り合い、関係を持つようになる。
晩鳥はキャリアウーマンの妻を持ち、中学生の娘もいるが、古書店の収入ははかばかしくなく、ネットオークションを中心に自宅で仕事をする日々。妻への強い思いはあるが、なんとなーく相手にされていない。
そこで「物欲しそうな主婦」の知子と関係を持つ。
二人とも、今の配偶者になんとなく満足していなくて、今の生活にも閉塞感を感じていて、そこで不倫。あんまりにもありきたりな設定だけれど、ま、小説はストーリーだけじゃあありませんよね。
二人の間にあるもの、露骨な性描写などは全くないんだけれど、淫靡でイヤラシイ。中年の不倫というのは、目的がはっきりしててゴチャゴチャしてませんね。
でも、関係を持てばいつかゴチャゴチャがやってくる。心の傷が深くなるのはどっち?
最後まで読んで、ちょっと怖くなった。
「遊び」と割り切っても最後に面倒なことになる。気をつけましょう
砂漠の塩 松本清張
砂漠の塩改版

作者:松本清張
テレビドラマや映画になることの多い清張作品。『砂の器』というずいぶん古い映画をこの間みたけれど、(加藤剛サマが犯人役だった!)本を読むのは(たぶん)初めて。
まだ海外旅行が珍しかった昭和40年ごろ。夫を日本に残しヨーロッパツアーに出かけた泰子だが、一人ツアーを抜け出してカイロに向かう。
そこには、出張先の香港から出てきた真吾が彼女を待っていた。つまり不倫旅行。二人はこの中東の地で、二人の愛を結実させるべく心中を考えていた。
泰子は真吾を愛しながらも、最後の一線を越えようとしない。ホテルも別の部屋をとる。男からすれば、「何なんだこの女」と思うだろうけれど、どうしても善良な夫、保雄のことを裏切る気になれない(とっくに裏切ってると思うんだけれど)
キリスト教徒ではないけれど、「神」のようなものが泰子の行動を束縛する。
保雄は思っても見なかった妻の出奔、不倫におどろき、エジプトに彼女を求めて行く…そこで悲劇。
不倫して海外で情死、なんてちょっと古い話で感動に至らなかった。無教養で、でも善良な(だって快く当時60万円以上する海外旅行に出してくれるんだよ!)夫に嫌気がさし、幼馴染の真吾を愛する泰子の気持ちもイマイチわからない。
ただ、海外旅行が珍しい時代にあって、中東の観光案内、文化のガイドブックとして読める側面もあり、当時としては面白い小説だったんだろうと推測する。
なんか、えらくバブリーな香りのする小説だった。