自負と偏見のイギリス文化

著者:新井潤美
昨日紹介したジェイン・オースティン。面白かったので、ちょっと彼女の世界を知りたくなって読んでみた。
ジェイン・オースティンを読んだのは『説得』のみ、『エマ』『プライドと偏見』は映画で見ただけなんだけど、いずれも英国のアッパーミドルクラスの恋愛模様を描いていて、印象としては(私は大好きだけれど)「オンナ子どもの読み物」だった。
しかし、イギリスでは中高等学校の「必読図書」で、卒業試験の課題図書にも必ず含まれているという。
男性ファンも多く、続編や翻案も書かれ、オースティンブームが続いているとか。
この本では、ジェイン・オースティンの生い立ちや若い頃の習作の紹介から始まり、主な作品の内容を引いて小説世界を解説している。
オースティンは「自分の知らないことは書かない」作家であり、自身もアッパーミドルクラスだったという。
貴族の結婚には「階級」意識が大いに働いていたこと、恋愛と結婚が若い女性の重要な問題であったことなど、オースティンの小説を読み解く入門書と言ってもいいかもしれない。
へーーー知らなかった、と思ったのは、『ブリジット・ジョーンズの日記』がオースティンの『プライドと偏見』『説得』の翻案だったということ。
映画しか見ていないけれど、これまた凄く面白かった。続編も。(ピーコとおすぎはバカにしていたが)コリン・ファースもヒュー・グラントも大好きなので・・・(コリン・ファース様、どうか肥らないで!)

現代イギリス文化にも受け継がれるオースティンの世界。読まず嫌いをせずに、あなたも読んでみては?
月別: 2009年9月
説得 ジェイン・オースティン
説得

作者:ジェイン・オースティン
イギリスの小説。1800年代初頭の作品。日本で言えば江戸時代後期で、伊能忠敬がなんかした頃。
准男爵の娘アンは27歳独身で、影の薄い存在。8年前、周囲から反対されて海軍軍人のウェントワースとの結婚をあきらめたことが彼女の心に影を落としている。
しかし、そんなアンに思いがけない再会が待ち受けていて・・・
虚栄心のかたまりの父と姉、ひがみ屋の妹、アンに近づく貴族男性など、個性的な登場人物が多く出てきてとっても分かりやすい話。100パーセント恋愛小説といってもいいかも。
しかし、貴族の生活って何なんだろうと思う。軍人は仕事してるっぽいけれど、男爵とかは、狩をしたり、交際したり、土地ころがしたり、実にヒマそうだ。女はもっと。人のことは言えないが、一日中遊んでいて人間関係にやきもきしている。
まあ、そういう文化だったんだろう。
ジェイン・オースティンの作品を読んだのは初めて。映画は
『エマ』

『プライドと偏見』

を観て、面白かった。衣装とか、風景とかもキレイ。
『ジェイン・オースティンの読書会』

という映画もある。
イギリスでは人気なんだろうな。この映画は、読書会で知り合った男女が恋に落ちるという話なんだけれど、オースティンの作品が男性の興味を惹くかどうかはちょっと疑問。
あくまでロマンチックだもの。
でも、読んだ本の話題で会話が続くなんて、ステキだ。
浪打ち際の蛍 島本理生
波打ち際の蛍

作者:島本理生
主人公の真由は現在休職中。元恋人のDVが原因で心を病み、今はカウンセリングルームに通っている。
同じくカウンセリングに通う蛍という男性と知り合い、徐々に二人は距離を縮めていく。
しかし真由は元恋人とのことが頭をよぎり、蛍に本当に心を開くことはできず、そんな自分にも苦しむ。蛍は我慢強く真由を思い続ける・・・
といった内容。恋愛のことが90パーセントを占めている。まあそれはよい。未婚の若い女子の頭の中は半分以上恋愛で占められているのが実際だから。
ストーリーはありきたりだけど、ディテイルは島本氏らしくとても繊細。過去の出来事を引きずって相手のことを過剰に窺ったり、身体の感覚の描写はうまいなあと思う。
しかし、「蛍」の人物像が明確につかめなかった。カウンセリングに通うほど重症でもないし、(たぶん)元カノとも平気で逢う。でもって、真由に身体のふれあいを何度も拒否されても非常に優しく、辛抱強い。
いい人だけど、好きになれないタイプだった。元カノと逢うという時点で不合格。友達に戻れるくらいなら真剣な恋じゃない!
などなど思いましたが、全体的には面白い小説でしたよ。
生きなおすのにもっていの日 田口ランディ
生きなおすにもってこいの日

著者:田口ランディ
『コンセント』『モザイク』などで有名な小説家のエッセイ。
小説は上の二作品ぐらいしか読んでなくて、最近この人の著作から遠ざかっていたのだけれど・・・
前半は主に世の「悲惨な事件」に対する思い。後半は講演の内容や日々思うことなど。
秋葉原の連続殺傷事件。幼い少女に性的行為を無理強いし、さらに殺してしまった男。
マンションに侵入し、隣人女性を殺害した男……。
平凡な私は許せない、酷すぎる、という感想しか出てこないけれど、田口氏の考察は深く深く広がっていく。
少学生の自殺を「うっかり自殺」と定義してみたり、死体をバラバラにする行為を太古の石器時代にまで遡ってみたり・・・
全体を通して、この世界は悲惨だけれど、人生も世界も私は肯定する、という姿勢を感じた。
この人はひきこもりの兄が餓死(!)したという経験を持っていて、エッセイの随所にそれが出てくる。個人的には避けたい体験・・・だけれども、作家としての原動力にもなっていそう。
不幸な出来事はその人の人生を変えてしまう。もちろんプラスの経験だと思えることは一生ないだろうけれど、経験を昇華して他の人へメッセージを伝えられるパワーはすごいなあと思う。
巡礼 橋本治
巡礼

作者:橋本治
橋本治氏の著作はエッセイなんかはたまに読むけれど、小説は
『勉強ができなくても恥ずかしくない1~3』

以来二作目。
主人公は下山忠市。70歳を過ぎ、今はワイドショーにも取り上げられるぐらいの「ゴミ屋敷」に住み、周囲の住人たちの非難の目にさらされている。
最初は下山の輪郭が全く見えず、住人がゴミ屋敷をひたすら迷惑がる描写や、下山の近所に住む老婦人の回顧が続くのだけれど、二章からは下山のそれまでの人生が長々と語られる。
戦時下に少年時代をすごし、敗戦後、豊かさに向けてひた走る日本を、ただ生真面目に生きてきたはずなのに、家族も自分の生きる道も失ってしまった。
不器用で孤独な男の一生。
「ゴミ屋敷」。ワイドショーではよく取り上げられるネタだけれど、私にはあまり興味が無い。近所に居たら困るけれども、その「住人」を理解しようとは思わない。だって、全く理解できないもの。
しかしゴミ屋敷の住人を主人公にして、その内面を掘り下げようとする作者の試みは流石だなあと思う。理解しあえないのが人間、ということを前提におきながらも、人間にはそれぞれの人の歴史があり、唯一無二の「魂」があるということを示している。
なんでこの小説が『巡礼』なの?と終盤までナゾだったけれど、最後に納得。
下山の人生は悲惨といえば悲惨だけれど、最後には一条の光が見えてジーンとくる。
大人向けの小説として素晴らしいと思います。
ゴミ屋敷の住人の見方が変わるかも・・・一ヶ月ぐらいは。
「生きる」ために反撃するぞ! 雨宮処凛
「生きる」ために反撃するぞ!

著者:雨宮処凛 湯浅誠氏と鶴見済氏との対談もある。
雨宮氏はもともとは右翼団体にいたらしいけれど、今は「反貧困」の活動家。「反貧困ネットワーク」の副代表。
この本は、「実用本」だ。実際に過酷な労働条件や不安定な生活にさらされる人のための「自己防衛マニュアル」。
フリーターでも労働組合に入れるとか、派遣先でぼったくられたらどうするかとか、明日の生活費がなくなったらどうするかとか、具体的なアドバイスがいっぱい。
やはり「知識で武装」することがとても大切だとわかる。雇用主でも知らない法律は多いらしいから。
そして、「団結」することも。一人で立ち向かうよりも、ネットワークに入った方が強い。
あとは、過酷な労働の現状。美容師・旅行添乗員の過酷な世界、外国人労働者の人身売買的なシステムなど。
私は運良く、今まで労働条件が酷すぎる!と思ったことはあまりないけれども、これから働くときには困ったことも出てくるかもしれない。そんなときはこの本を読み返してみようと思う。なかなか強気には出られないけれど・・・
一番「ほほう」と思ったのは「セクハラにあわない方法」。雨宮氏は数々のセクハラを受けたが、「ゴスロリ」ファッションにしてからというもの、セクハラどころか好きな男性にも相手にされなくなったという。
なるほど・・・私自身はひどいセクハラに遭った事はないけれど、これも一つの方法。
美しく生まれついて、あるいは気が弱そうに見えてしまってセクハラに遭いがちな方には非常に有用なアドバイスですな。
トライアングル 新津きよみ
トライアングル
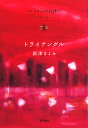
作者:新津きよみ
主人公は郷田亮二という駆け出しの刑事。医学部を卒業して医師になったが、医師を辞めて刑事になったという変わった経歴の持ち主。亮二のこの経歴には、過去に遭遇した事件が大きく影響していた。
十歳の時、初恋の少女・葛城佐智恵が誘拐され、殺されたのだ。事件から十五年が経って時効が成立した時、亮二は自ら刑事となって、この事件を追い続けることを決意した。
そんな亮二の前に、「葛城サチ」と名乗る美しい女性が現れた。よりそう母は葛城佐智恵の母。どういうこと?
事件から20年後の同窓会にふらりと現れたサチ。謎は深まる。真犯人は?サチの正体は?
新津きよみ氏の小説を読んだのは初めて。
前半はとても面白かったけれど、後半に入ってちと失速。サチの出生の秘密、真犯人、主人公の恋、どれもなんか「深み」「説得力」がない。
読み終わった後で知ったんだけれど、今年の冬テレビドラマになっていたらしい。江口洋介、広末涼子などが出ていたとか。いっぺんも見てないけれど。
ドラマ化されることを意識した小説なら、なるほどという感じ。文章の力というよりも、分かりやすいストーリーで読ませる小説だった。
僕は、字が読めない 小菅宏
僕は、字が読めない。

著者:小菅宏
南雲明彦さんという24歳の青年(表紙の写真にあるように、なかなかの好青年)が、読字障害(ディスクレシア)と闘い続けた記録。南雲氏へのインタビューと、母の日記が中心になっている。
読字障害というのは学習障害の一つ。文字を読むのに人一倍時間がかかったり、文字をまとまりで理解することが出来なかったりするという。程度は人によってそれぞれ。
会話のコミュニケーションにはまったく困らない。
読字障害をカミングアウトしている人は海外に多い。有名どころではトム・クルーズ、ウーピーコールドバーグ、などなど。医師や小説家にもいる!
知能が低いわけではなく、苦手分野があるだけということ。でも、文字を使うことが必須の文化であるために日常に非常に支障が出る。
私も「さかあがり障害」で「軽い方向障害」だけれども、日常に支障はない。
読字障害がいかに本人を苦しめるかということは本を読めばわかる。苦しさの歴史、という感じだ。
南雲氏は数回の自殺未遂を繰り返し、高校も途中からいけなくなり、引きこもりになった経緯がある。
黒板を写すのに時間がかかって勉強についていけない、アルバイトはすぐにクビ。「なぜ自分はこうなのか」ということがわからない。
でも、自分が典型的な「読字障害」ということを知ったことで本人も家族も気が楽になったという。
学習障害とか、アスペルガー症候群とか、近頃よく言われるようになったけれど、大切なのは本人も親も周囲もそのことを「知ること」だとわかる。知ることによって対処もできるし、「適材適所」の仕事が見つかる可能性もある。
「頭が悪い」「異常に空気が読めない」と普通のものさしで判断して悲観する前に、現実を知ることの大切さを知った。
わたしたちが孤児だったころ カズオ・イシグロ
わたしたちが孤児だったころ

作者:カズオ・イシグロ 訳:入江真佐子
ちょっとミステリめいた長編小説。
1900年代初め、上海で暮らしていた英国人クリストファー・バンクスは十歳で父母が行方不明になり、孤児になった。
貿易会社に勤める父と美しい母。どうやら当時問題になっていたアヘン貿易絡みの事件に巻きこまれたらしい。
イギリスに戻り、伯母の助けで名門大学を出て探偵になったクリストファーは日中戦争が勃発し混迷を極める上海に両親を探しに舞い戻る・・・というお話。
10歳で両親と生き別れたら、両親像は「聖なるもの」になるだろうけれど、果たしてやっと判明した両親失踪の真相はいかなるものだったのか。人生はそれほどスイートではない。
同じく上海で子ども時代を過ごしていた幼なじみの日本人、アキラや、クリストファーがひきとった孤児のジェニファーなど、誰もが「孤児」の側面を持つ。
20年も昔の事件のために戦争中の上海にのりこんでいくなんて、ちょっと非現実的なんだけれど、カズオ・イシグロならではの静かな筆致で許される感じ。
懐古的で上品なミステリ、といった趣でした。
小沢主義 小沢一郎
小沢主義(イズム)

著者:小沢一郎
昨日に引き続き、民主党のお勉強。具体的な政策には余り触れていない。どちらかというと「リーダー論」みたいなものが印象に残った。
まずは選挙の話から。昔ながらの「ドブ板選挙」こそが民主主義の原点であるとしている。人々の声に耳を傾け、徹底的に選挙区を回ること。そういった選挙活動が政治家を作っていくとも言っている。
政治に関しては、過去の「自社対立」はウソだったというのが面白かった。水面下ではがっちりと連係プレイをしていたと。小沢氏といえば小選挙区制を導入したことがよく知られているが、政策論争を形式化しないための狙いだったという。
リーダー論について。日本の社会の「和を以って尊しとなす」という雰囲気が真のリーダーを生まない土壌になったとし、傑出したリーダーが日本を変革した歴史にも触れている。
小沢氏が尊敬するのは織田信長、大久保利通。万人から好かれなくても、批判が多くても、一切の妥協しなかった彼らだからこそ社会を改革できたのだと。
小沢氏はリーダーの条件を「自分の目指すものを明確に揚げ、自分で決断し、自分の責任において実行できる人物」と述べている。「志、理想、ビジョン」がなければ人を導けないし、人はついてこない。
「誰も責任をとらない」というのも日本社会のよくない点のひとつであり、教育の欠陥もそこにあるとしている。
あとは、歴史に学べということ。リーダーには必須の条件だと。確か勝間和代氏の本にも「愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ」と書いてあったような。
レキジョから程遠く人に嫌われるのがコワイ私にはリーダーはムリかも・・・
テレビではほとんどまともに喋らない(失礼!)小沢氏の考えの一端を知るにはよい本です。