閃光

作者はノンフィクションライターでもある永瀬隼介。
玉川上水で男性の扼殺体が発見される。捜査陣に名乗りを上げた、あと少しで定年の滝口と相棒に選ばれた巡査部長の片桐。
滝口はこの殺人事件に三十年以上前に起きた“三億円事件”との接点を見いだす。その頃、殺された男と三億円事件当時仲間だった連中が再会していた。
昭和最大のミステリーと言われる三億円事件にある仮説を呈した興味深い作品だった。
かなりの長編で、読むのにちょっと疲れた。私としたことが三日もかかってしまった。
でも、読み進むうちに面白くなってきて、だんだんスピードアップ。警察という組織の闇、階級社会の厳しさもリアルに描かれていたし、三億円事件の犯人像もこんなんかも、と思ってしまうストーリーの面白さがあった。
ニュースで事件を知っても、そこから深ーく洞察する人と、表層しかなぞらない人がいる。
私は後者。あまり背景を洞察したりはしない。
作家になる人っていうのは、(特にミステリなんかの場合)その背景とか人間関係とか、ウラのウラまで考える人なんだろうなと思う。
この小説も人間のウラのウラまで考えることで出来ている。
読み応えのある一冊です。長編ミステリを好む方には是非お勧めします。
月別: 2009年6月
向田邦子の手料理 向田和子
向田邦子の手料理

向田邦子氏の妹、向田和子氏の監修で作られた本。
10代終わりから20代前半まで、向田邦子の大ファンだった。小説、随筆はすべて読んでいた。
特に随筆。『父の詫び状』が有名だけれども、どの随筆もすばらしくて何度も繰り返し読んだ。
その勢いでこの本も20代前半ぐらいに購入したと思う。今も本屋で売られていて、版を重ねているんだー、と嬉しくなった。
見て読んで、試しに作って、とても楽しい本。料理だけではなく、家族とのエピソードや食にまつわるエッセイ、向田氏の友人たちの寄せた文章もある。
文章のセンスはもちろん、料理のセンス、洋服のセンス、生き方のカッコよさ、私の憧れの女性の一人だ。
向田氏の若い頃の写真もいっぱい。彼女はすごい美人というわけではないけれど、ハッとするほど美しい。センスのいい女性は、自分を美しく見せることも得意なんだと思う。
「プロに撮ってもらった写真?」と思うほど素敵に撮れているものが多いんだけれど、後に向田氏がひそかに交際していた男性が撮ったものだと判明して、ああ、なるほど、愛に溢れているわけだ、と納得した。
近頃暑くて、台所に立つのがおっくうになってきた。料理本でも見てヤル気をださないと、と思ってこの本を本棚から引っ張り出す。
今晩は「にんじんご飯」にしてみようかなー。「トマトと青ジソのサラダ」もさわやかでいいかも。
古文を楽しく読んでみる 松尾佳津子
古文を楽しく読んでみる

筆者は主に河合塾で古文を教えているという松尾佳津子氏。
教科書に出てくる古文は、いくぶんつまらない。教育的によろしくないものはまず載らない。
この本では、入試問題を題材にしていろいろなタイプの古文を紹介し、その面白さを解説している。
いやー、へんなものを入試に出す大学があるもんだ、と感心。駿河台大学の『一寸法師』とか、法政大学の『女殺油地獄』とか。
『一寸法師』の原典が実はかなりひどい話だと知ることが出来てよかった。
古文は、ほとんどの高校生に苦手意識があるのではと思う。文法をマスターし、単語を覚えるのはそこそこの努力でなんとかなるけれど、内容の理解は難しい。
古文は省略が多く、主語もわからず、「行間」を読まなければ理解できない。
「行間」が読めるようになるには、背景知識や古文常識みたいなものが重要になってくる。
古文の背景を知るにはよい本かも。読み物としての面白さは、まあ、普通…
予備校講師の書いた古文にまつわる著といえば、「マドンナ古文」の荻野文子氏が書いた
ヘタな人生論より徒然草

は素晴らしかった。超オススメです。
絵のある人生 安野光雅
絵のある人生

画家の安野光雅氏による著。
絵を見る楽しみ、描く喜びについて、語り口調でさらりと書かれている。
油絵を水彩画、写実と中小、画家の生き様など、絵画の世界の案内書になっている。美術評論家の文章ではなく、絵を描く主体ならではの解説という感じ。
これから絵を描こうという人のためのかなり具体的なアドバイスもあり。私は不器用で、絵は見るだけなのでここはいい加減に読んだけれど、読書案内までしてあって、「これは読もう!」というものもあった。
絵を描く人生は絵を描かない人生に比べて充実している、と最後に筆者は述べる。
絵はお腹の足しにはならないけれど、いい絵を見るだけでも人生が充実すると思う。
ずーっと前に、島根県は津和野にある「安野光雅美術館」に行った。とてもよかった。そこで『あいうえおの本』という絵本を買った。

絵を見る喜び、面白さを存分に味わえる絵本です。
学生の頃、画廊でアルバイトをしていたときに、元中学教師の絵描きのおじいさんが、「街の子は田舎の子に比べて絵のセンスがあることが多い」と言っていた。
私は家の周りは田んぼだけ、シカが出るような田舎に住んでいたのでちょっとショックだったが、子どもの頃からいろんな色彩や文化に囲まれていたらやはりセンスがよくなると思う。
パリに行った時、有名な美術館で学校の遠足と思われる小学生たちをよく見た。パリっ子のセンスのよさは一朝一夕のものではないのね・・・と思ったことを覚えている。
まあ、今からでも遅くはない。絵でも見に行きたいなーと思ってしまう本でした。
劇場 モーム
劇場22刷改版

イギリスの作家、サマセット・モームが63歳の時に著した小説。
1937年の作品だけれど、ちっとも古く感じなかった。面白かった!
主人公は舞台女優のジュリア46歳。夫のマイケルは男前の俳優兼劇場経営者。ロジャーという一人息子をイートン校に通わせている。
彼女は女優として成功していて、夫とも円満、彼女を20年崇拝するプラトニックな男友達もいるが、たまたま劇場の経理を担当した23歳のトムに誘惑され、恋に落ち、彼に夢中になる。
二人の蜜月はそれでも長くは続かない。トムの心が新人女優に傾いたとき、ジュリアはどうしたか・・・
「女優」「女」というものの業が見事に描かれていた。
ストーリーも最高に面白いけれど、ジュリアがいつの場面でも「女優」であるところが怖い。
恋に落ち、自分を見失っても、その恋が冷めたときにも自分の心を冷静に見つめる。
ジュリアのファンになってしまった。
女心の機微を描くモームの力にも感服。
ジュリアから見ると愚鈍でつまらない息子のロジャーが、実は虚飾に満ちた両親の本質を鋭く見ていた、という最後もよい。
女優というのは天賦の才能なんだと思う。例えば大竹しのぶ。カメラが右から来たらそっちの眼から涙を流せるらしい。
他にも、女優さんが演技以外で喜怒哀楽を示しているのを見ると「演技かな?そのぐらいお手のものだろうな」と思ってしまう。
この間結婚された川島なお美さん。キレイでしたねー。でも感涙の場面では「ほんとに涙流れている?」とじっと画面に見入ってしまった。意地悪な私・・・
本の話に戻れば、これは超おススメです。ハラハラして、スカッとします。恋人は裏切るけれど、仕事は裏切らない!
水上のパッサカリア 海野碧
水上のパッサカリア

作者は海野碧。
光文社のミステリ小説新人賞受賞作。
自動車整備工の大道寺勉は3年半前からQ県にある湖畔の借家で、一回り近く年下の片岡菜津と穏やかに暮らしていた。半年前、暴走族の無理な追い越しによる交通事故に巻き込まれ、菜津が死んだ。
その後、勉は菜津が育てた飼い犬のケイトと静かな暮らしを続けていた。
ある日、勉が帰宅すると昔の仲間が家の前で待っていた。菜津は謀殺されたのだという、衝撃的な事実を携えて…。
この本は、昨日紹介した「読書相談室」で薦められていたので読んでみた。
ミステリ、というよりハードボイルド。一級自動車整備士の裏の顔は「シマツ屋」。
アメリカのサバイバルキャンプに置いてけぼりにされたという過去を持つ屈強な男だ。
ハードボイルド・・・正直あまり得意ではないので、ちょっと小説が冗漫に感じた。
マッチョな男は好きだけれど、ハードボイルドの主人公は「女?消耗品。なくたって生きてはいけるさ・・・」という感じで、かわいくない。
でも、前半の菜津とのなれそめや、「なんでこの男金に困っていないんだ?」という謎が明らかになっていくところは、なかなか面白かったと思う。
ハードボイルド好きにはいいかも。「ミステリ」は期待しないで・・・
よりぬき読書相談室 本の雑誌編集部
よりぬき読書相談室(疾風怒涛完結編)

本の雑誌編集部編。
毎日本を読んでいるけれど、さて次はどんな本を読もう?と悩んでしまうことがある。
ついつい傾向も偏りがち。なのでときどきこういう読書案内に頼る。
さすがは本のプロ。読者の「こんな本が読みたい!」という相談に対して、ポンポンお勧めの本が出てくる。
ジャンルもミステリ・時代小説・SF、恋愛小説、エッセイなど多岐にわたっている。
または「元気になりたい!」「笑いたい!」「失恋から立ち直りたい!」などの相談にあわせて、本を紹介したり。
すごいな、と思ったのは「こういうストーリーなんだけど、題名がわからなくて」という相談にもちゃんと答えているということ。さすがはプロだ。
この本も、読みたい本をメモしながら読んだ。また本との出会いが楽しみ。
私も以前、若者から、どんな本を読んだらよいかよく相談された。でもすぐ出てこなくて困った。よく薦めていたのは山本周五郎の『さぶ』。読んだ子からは「よかった!」という感想も多かった。
相手を見て本を薦めることも重要。あんまりマジメな子にエロい場面の多い作品は薦めにくかったり。男子と女子でもちょっと違う。
今なら「ブログを見てください」と言うけれど。
顔 横山秀夫
顔
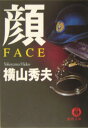
作者は横山秀夫。
23歳の婦人警官、平野瑞穂を主人公にした連作小説。
瑞穂はもと警察の鑑識課。「似顔絵」を書くことを仕事にしていたが、ある事件で挫折し、秘書課へ異動した。
新聞記者との攻防、銀行強盗、婦人警官銃撃事件・・・その中で瑞穂は躓きながらも自分の仕事にひたむきに取り組もうとする。
かっこいいヒロインではないけれど、徐々に成長していく姿に好感が持てた。
今朝の新聞にも「似顔絵警官」が載っていた。言葉の情報だけで、記者の顔を描く。写真ととても似ていたので、たいしたもんだ、と思った。
警察官って、まずは「観察」ということを叩き込まれるんだろう。人を疑う商売というのも面倒そう。
でも、人間て本気で観察してたらいろんなことが分かるんだろうなとも思う。
さて、この本は警察ドラマを5本、時短で楽しめる感覚の本でした。
でも短編はやっぱりちょっと物足りない。横山秀夫といえば

これは最高に面白かった!新聞記者のエゴイズムがリアルに描かれています。
読むだけでなんか暑くなってきます。
獄窓記 山本譲司
獄窓記
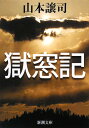
筆者は元衆議院議員の山本譲司氏。2000年に政策秘書給与の流用事件を起こし、01年に実刑判決を受けた。
433日に及ぶ獄中での生活を綴った著。新潮ドキュメント賞受賞作品。
とても読み応えがあった。2000年の事件のことはあんまり覚えていなかったけれど、この本を通じていろいろと考えさせられた。
まずはとても刑が重かったということ。執行猶予つきが予想されていたけれども、実刑になってしまった。同じ様なことをしている人(辻元清美氏・田中真紀子氏)は刑務所に入るまでにはならなかったのに(辻元氏は執行猶予)。
一罰百戒とはいうけれど、ちょっと気の毒に思わざるを得ない。もちろん、詐欺をしてはいけないが。
服役するちょっと前に第一子が生まれたというのも悲劇。
服役した著者の刑務所での仕事は、障害を持った同囚たちの介助訳だった。
汚物にまみれる、果てしのない作業。受刑者に人権なんてあったものではなく、(あたりまえなのかもしれないけれど)劣悪な環境に耐えなければならない。
私は単純。「文は人なり」と思って、文章から読み取れることをすぐ信じるのだけれど、山本氏は悪いことはしたけれど、腐ってはいない人なんだろうと思った。
奥さんとの信頼関係がずっと崩れなかったのも一つ。
率直に反省し、潔く刑を受けたことが一つ。
誰が見ても「厳しすぎ・長すぎ!」の服役の期間を、自分が生まれ変わった契機として前向きにとらえていることが一つ。「障害と犯罪」の問題を新たなライフワークにしようとしている。
もちろん、前向きになるには待つ家族の力が重要だとは思うけれども。
誰だって罪を犯す可能性はある。罰を受ける可能性もある。でも、そこで自分が反省して生まれ変わればまた新しい目標を持って生きていけるもんだ。人間の底力に感心した。
いまだに「自分は悪いことをしてない!」と反省の色ナシの辻元氏と山本氏が早稲田で同じゼミだったとか。
まあ、高潔だからといって幸福とは限らないけれど、辻元氏が活躍するのはなーんとなく面白くないなあ、と思ってしまった。
ミッキーかしまし 西加奈子
ミッキーかしまし

筆者は西加奈子。若い読者に人気の小説家ということは知っていた。
この人の小説、実は読んだことがない。かなりヤング向けなのかな、と思って。
作家のエッセイはファンのためにあるもので、ただの身辺雑記、面白くないことも多いけれど、これは相当面白かった。
声を上げて笑うこと数回。
作者はテヘラン生まれのエジプト育ちという経歴を持つ。子どものころのエジプトのエピソード。こんな体験を持つ人が周りに居ないのでとても興味深い。
数々のアルバイトでの経験。日常の瑣末なこと。
エジプト以降は大阪で育っているせいか、ものすごい笑いのセンスをかんじた。
筆者自身のイラストもよい。
小説でもセンスのいい作家かもしれないと期待。食わず嫌いはやめて、こんど是非小説の方も読みます!