藤堂志津子の短編集。藤堂志津子の小説って、読んだ後に「あーさわやか!」って気分になることはめったにない。この短編集もかなりどんよりする。
気味が悪い。オカルトではないんだけど、日常生活を描きつつ、まっとうな人間の顔がべろりと妖怪じみた表情になるかんじ。
中年以降の、性、仕事、金、いろんなことが絡まって面倒な人間関係を描いている。ちょっと性質のよくない人、ダメな人ばかりが出てくる。主人公自身もかなりダメな感じ。
でも、これも一つの人間の真実なんだろうと思う。「お金」のことをうまく避けて書く作家も多いけど。(夏目漱石とか村上春樹とか吉本ばななとか、高等遊民ばっかり!)
藤堂志津子の小説に出てくる男性は、なんだかナルシストでいやーな奴が多い。面食いから足を洗えず、手痛い失敗を重ねてきたのでは?と邪推してしまう。

月別: 2009年1月
ミスター・ヴァーティゴ
「vertigo」とは「めまい」の意。なぜ「ミスター・ヴァーティゴ」なのかは物語の中盤まで読まないとわからない。
伯父のもとで育ったウォルトは、九歳のとき、イェフーディという男に引き取られ、空中浮揚の修行をさせられる。厳しい修行の末、浮揚できるようになり「ウォルト・ザ・ワンダーボーイ」として人気を博し、金を稼げるようになる。だけど悲劇も待っていて…
77歳になったウォルトが9歳からの人生を振りかえるかたちで物語は進む。まさに浮いたり沈んだりの過酷な人生。禍福はあざなえる縄の如し!というストーリー。おとぎ話ではあるんだけど、読み応えがあった。
寓話だから、人生におけるさまざまな要素が示されているようだけど、それをいちいち読み解くのは私の趣味ではない。(というか、できない)
一人の人間の成長物語として、面白く読めた。愛を知らない少年が、愛を知るようになる。そこが好き。浮き沈みの激しいウォルトの人生。トータルで見たら「沈み」の方が大きいんだけど、それでも愛を知らない人生よりは、マシだ。

また会いたくなる人 婚活のためのモテ講座
きのうの新聞紙上で見たのだけれど、女性誌の「anan」が「婚活」特集をしていた。
私の学生時代「セックスできれいになる」というセンセーショナルな特集を組んだanan。
友達がコンビニで買っていたなあ。ちょっと見せてもらったりしたなあ。
前衛(?)だったananも結婚特集を組むようになったかーと時代の流れに感慨。
さて、『また会いたくなる人』の著者はNPO法人花婿学校(!)の主宰者。「はじめに」に、「結婚できる人」について、男性は「高収入(=仕事ができる)または人間力(コミュニケーション力)が高い。」女性は「外見をキレイに魅せるのが上手である」と書かれていて、真理はここに集約されているなあ、というかんじ。
女は金持ちで自分をチヤホヤしてくれる男が好きで、男はとにかく美人が好き、ということだろう。納得。
著者自身、「モテない君」を克服した経緯があり、服装からメールの作法まで、アドバイスは具体的で実践的。本気で結婚したいけど、なかなか縁に恵まれず、縁が続かない人にはオススメの本。
一方『結婚ライセンス』。トンデモ本のカテゴリーに入れたい。女性は若くて美しくて…がよい、というのは『また会いたく…』の本と本質的に違わないのかもしれないけど、日本女子大の先生が書いていて、なんか高みからものを言ってる感じがした。最初に「結婚に適しているか」みたいなチェックリストがあったけれど、それによれば私は不適格者。そんなバカな!
保守的な考えを素直に受け入れられる人にはよい本だと思うけど…
「婚活」ってやはりブームなのか?婚活ビジネス、栄えはじめているんだろうな。


大人の友情
この本に書かれていた、ユング派の学者の祖父の「友情」の定義を紹介する。
「夜中の12時に、自動車のトランクに死体を入れて持ってきて、どうしようかと言ったとき、黙って話しに乗ってくれる人」だそうだ。
そんな状況は避けたいけれど、自分があてにできそうな友人、そして自分が黙って話に乗ってあげられそうな友人を思い浮かべてみた。まあ、4,5人ってとこかな。
夫に聞いてみたら、彼は仮定の話が好きではないので「ありえない」という感じだった。
色気の少ない青春時代だったためか、本気で「宝物は友達!」と思っていた。遊んだり、おしゃべりしたりが何よりも楽しくて、学校も大好きだった。今はみなそれぞれ家庭を持って、子育てが大変な時期の子もいて、昔みたいには会えないけれど、それでも会えば同じことで笑えて、悲しいときには一緒に泣いてくれる。みんなで長生きしたい。
『大人の友情』では、一般的な友達だけではなく、夫婦間、男女間、師弟、家族…さまざまな人間関係を貫く友情について、具体的なエピソードを交えて語られている。師弟や男女なんかは一般的に友情は成立しそうにないけれど、それでも関係をつなぐひとつの要素として友情を
語っていて興味深い。
家族内で将棋、トランプなどのゲームをすることの大切さについて書かれているところは「なるほどー」と膝を打ちたい気持ちになった。
大人になったら、友達はいつもそばに居てくれるとは限らないけど、「友情」がなかったら人生はつまらないと改めて思った。

恋と恋のあいだ
フツーの恋愛小説。淡々と恋が進み、なんとなくうまくいく。あんまり誰も傷つかない。
ドラマチックさに欠けていて、物足りなかった。
ただし、文章はキレイで、美味しそうな食べ物が描かれているところは好き。
「はんぺんのなっとう和え」これはやってみようかなー。
モテ系、非モテ系、と恋愛小説をカテゴライズしているけれど、恋愛小説を描く女流作家について、この人はモテている人生か、あんまりモテていない人生か、なんとなく予測できる。
美醜に関係はなし。独断と偏見に基づく予測。
モテて来た人…野中柊、江國香織、村山由佳、谷村志穂、川上弘美、田辺聖子、和泉式部
モテなかった人(痛い思いが多い人)…山本文緒、林真理子、藤堂志津子、唯川恵、紫式部
などなど。今思いつくのはこんなもの。角田光代は微妙。
モテなかった人の文章からは、なんとなく潜在的な男ギライを感じる。
しかし、男性の描く恋愛小説…吉田修一とか石田衣良とか辻仁成とか藤田宣永とか、みんなモテそうだ。モテなかった男の描く恋愛小説って、ちょっと読みたくない、というのは偏見かー。

ラッシュライフ
この本、一年以上前に購入して、最初だけ読んで、なんか読めなくて、放置していた。たぶん疲れていて読めなかったんだと思う。
私にとっては初、伊坂幸太郎作品。今改めて読んでみて…
久しぶりに「この人天才!」と思った。
5つの視点から事件、人生が描かれていて、最初はエピソードがバラバラなんだけど、終末に近づいてすべてが収束していく、という群像劇。作者は映画ファンらしく、面白い映画みたいな作品だった。随所に、映画や小説の影響が感じられる。
犯罪を扱う小説にも、愛や倫理があっていい。ディテイルに魅力がないとストーリーがよくてもつまらないけど、魅力たっぷり。「ミステリ界の村上春樹」と言ったら言い過ぎかな。
同作者の「アヒルと鴨のコインロッカー」は、映画で見た。期待以上に面白い作品だった。
基本的に、愛が溢れているし、瑛太がサイコーによかった。原作も読んでみようかな。

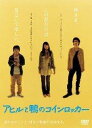
私という運命について
新聞の書評で、売れている本、とあったので読んでみた。
大手企業に勤めるキャリアウーマン亜紀の29歳から40歳までを描いている。その年に起こった社会現象や事件なども書かれていて、亜紀の生きた時代は特定できる。
キーワードは「運命」。出会い、別れ(とくに死別)を通して自分の運命を凝視し、振りかえり、驚愕する亜紀。あんまり救いのある小説ではないけれど、主人公の内面的成長、変化を丁寧に描いている。
登場人物がみんな「平均以上」で恵まれたバックグラウンドを持っている点がちょっとなー、と思ったけど、それでも悲しい運命には支配されている。
亜紀が自分の過去の選択について驚愕したり後悔したりしているところは、面白いと思った。
「後悔はしてない」って、言い訳のように言う人は多い。私も自分の選択を後悔するなんて大嫌いだから、あえて考えない。でも亜紀は後悔から逃げていない。これを描いている点は優れていると思った。
人は悲しみとか苦しみとかを通してこそ、内省的になるのですね。

古道具 中野商店
恋愛小説のカテゴリーにいれようかと思ったけど、恋愛中心とは言えないため、ほのぼの小説に入れた。
古道具屋でアルバイトをするヒトミ。店主の中野さんやその姉、周囲の人々の小さな事件を描写しながら物語は続いていく。同じくアルバイトのタケオとは付き合ってるような、付き合ってないような。タケオの言動に敏感に反応するヒトミの描写がよかった。
この小説は、フリーター小説とでも名づけたくなる。20代半ば、そこそこ歳はいっているけれど、自分の足元はフラフラしていて、だからこそ周りの出来事を興味深く見られているような。
長嶋有の「夕子ちゃんの近道」もテイスト、設定が似ている。西洋骨董品店の二階に居候している「僕」と、そのご近所さんたちの物語。恋愛はナシ。
長嶋有は男性だけど、植物的な印象。ギラギラネトネトした性欲など、持ち合わせていないかのように女性を描く。ちょっと依怙地で訳ありな女性を描くのがうまく、視線はあくまでもやさしい。
どちらの本も、ほのぼのした時間を過ごしたいときにはおすすめ。


八日目の蝉
角田光代にしては珍しい、犯罪を扱った小説。今まで読んだ角田作品の中ではナンバー1だと思う。
1章目は希和子の視点から描かれている。
恋人だった男その妻の家から、赤ん坊を盗み逃走する希和子。希和子は男の子どもを身ごもったことがあるが、やむなく中絶し、男の妻から「がらんどう」と言われた経緯がある。
希和子は曲折を経て、エンジェルホームという女性だけの宗教団体のようなコミュニティに逃げ込み、そこからまた小豆島へ逃げる。薫、と名づけた赤ん坊と一日でも長くいられるように祈りながら生活する希和子。こちらもつい感情移入してハラハラしながら読んだ。
2章目は薫改め、4歳で両親のもとに返された恵理菜の視点から描かれる。
恵理菜は18歳になっているが、一人暮らしをし、両親との関係はよくない。
恵理菜自身も不倫の子を身ごもって…
希和子のしたことはとんでもない犯罪だけれども、同情すべき点もある。犯罪がその後の被害者の生活や心に傷を残す深刻さもある。なかなか割り切れない。ストーリーもディテイルも面白くて見事。互いを分からぬまま希和子と恵理菜が会うラストシーンでは涙が出てきた。
ちょっと似たストーリーで、「子宮の記憶」という映画もあります。主人公の男の子が柄本明の息子で、ちょっとイケメンではないのが残念だけど、松雪泰子がすばらしく良いです。
松雪泰子って、素顔はきっと単純で素直な女の人だと感じるんだけど、演技するといいんだよなあ。


チエちゃんと私
昨日は吉本隆明を紹介したので、今日は娘のばななの本。
親戚のコネでイタリア雑貨の店に勤める42歳のカオリは、35歳のいとこのチエちゃんと一緒に暮らすことになる。
複雑な育ち方をしたチエちゃんは掃除と味噌汁作りだけをして、あとはずっと家にいるだけだけれど、カオリにとってかけがえのない存在になる。
相変わらず「へたうま」な感じの吉本ばななの文章だけれど、はっとする一文にいくつか出会えた。人間の相性の真実が描かれている感じ。
中年にさしかかろうとするカオリは、自分の感覚だけで人とかかわろうとする、そこが素敵だった。
オバサンになってくると、先入観だけで人を見たり、なるべく他人から影響を受けたくなくなったりする。お金とか仕事とか性とかがいろいろ絡んで、大人になってから友人を作るのは本当に難しい。
それでも相性のいい人にはまだ出会えるのかも。
ちょっと元気になれた。
